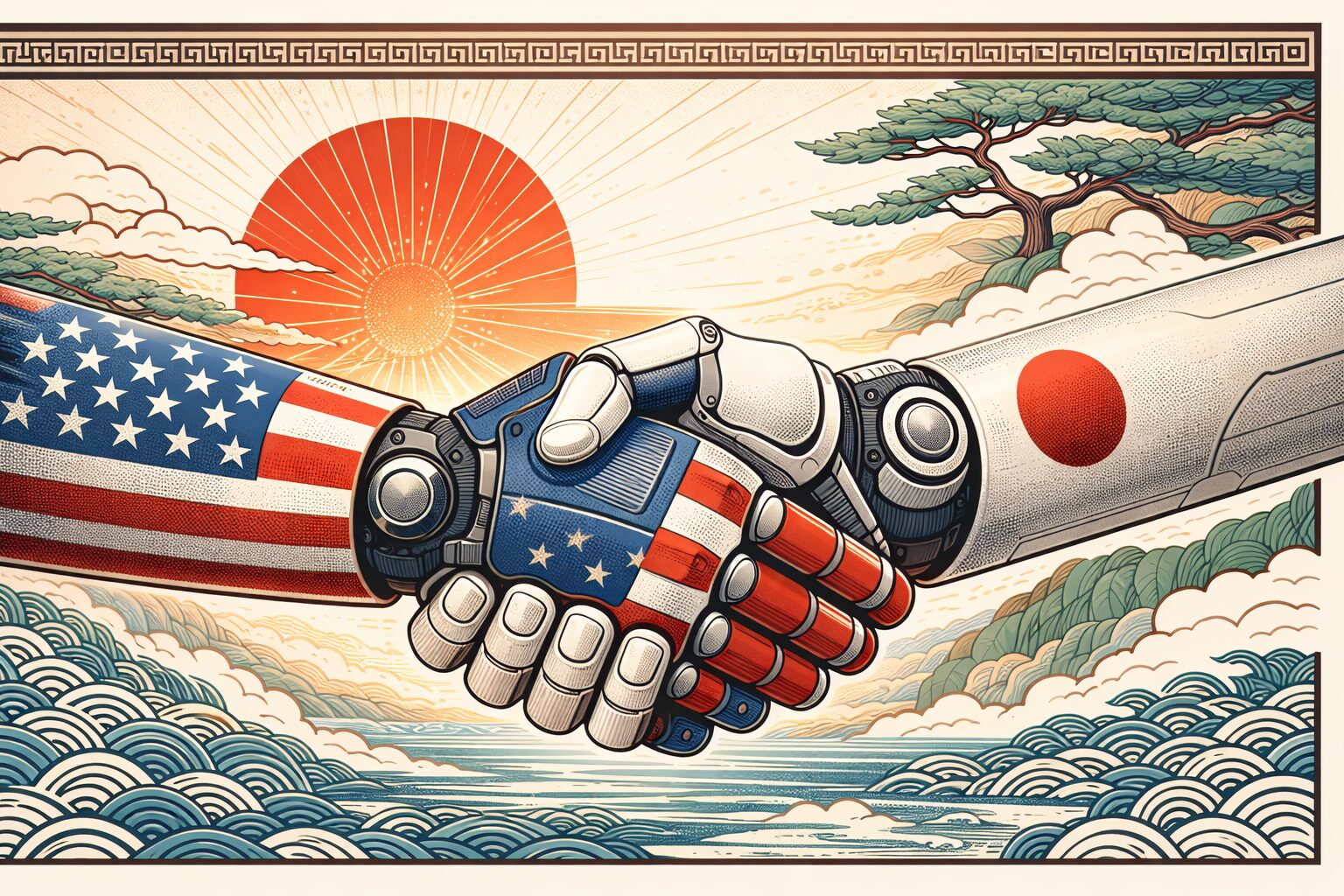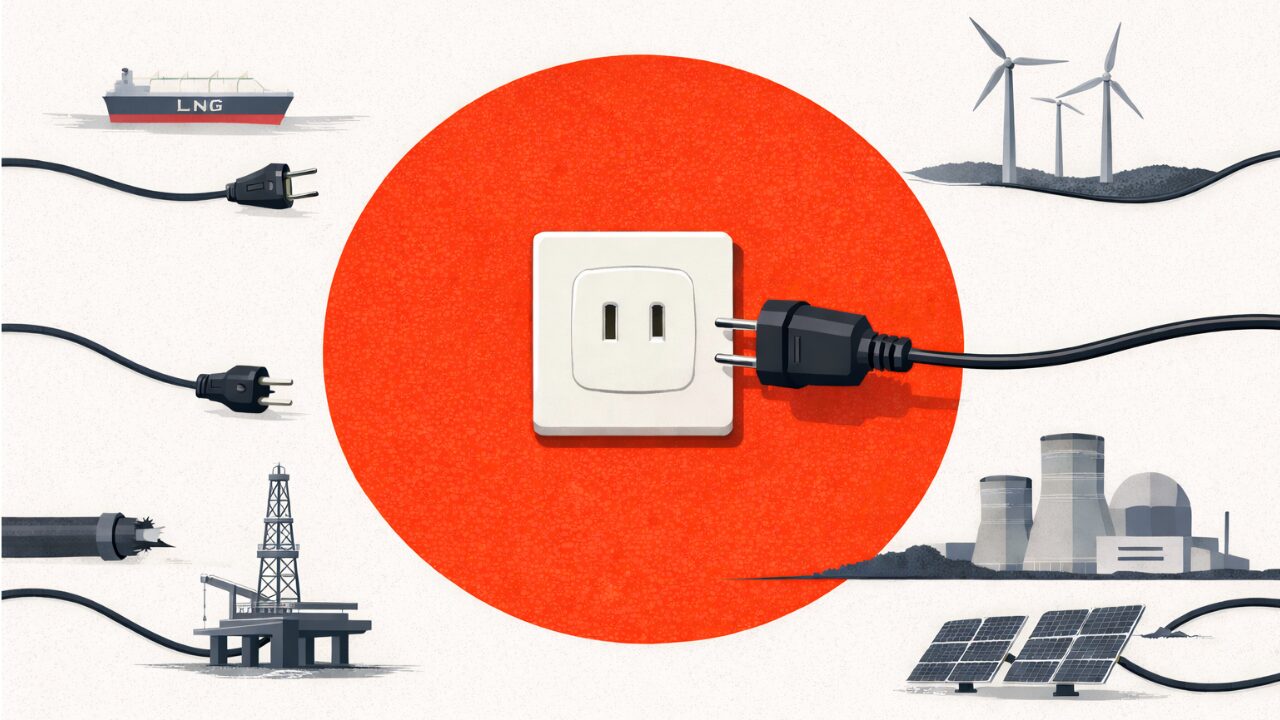最近、新聞やビジネス書の新刊コーナーを賑わす「DX」(デジタル・トランスフォーメーション)というのは、何のことでしょうか? 私たちCoral Capitalがお話する起業家の方々の中でも、DXという言葉を使う人が少しずつ増えています。ただ、指し示している範囲がきわめて広く、人によってどうもニュアンスが違うようです。
IT業界に長く身をおいてきた人や、xTechスタートアップで企業や産業の革新に取り組んでいるような人であれば、デジタルを使って事業や組織を変革しようとか、あるいはデジタル・ネイティブなアプローチで産業を再定義しようということは、もう10年も20年もやってきたことではないか、なぜ今さら新しい名前を付ける必要があるんだと感じているのではないでしょうか。「バズワードだ」「単なるマーケティング用語だ」と思う人もいると思います。どちらかと言えば私も、そう感じているタイプです。
ただ、ここのところ少し各国のレポートやDX関連書籍を読んでみて、これは過去5年ほどで潮目が変わったことを象徴する言葉なのかもしれないということに、(やっと)気づきました。そして日本企業については2つの大切な視点があるように思えます。このブログでは少し「DX」というトレンドが生まれた時代背景と、日本の大手伝統企業が置かれた状況を考察してみたいと思います。
2011年のミーム:「ソフトウェアが世界を飲み込みつつある」
「今後あるゆる産業領域においてソフトウェアが最も得意な企業が、その産業における勝者になる」
これは2011年に「Software is eating the world」(ソフトウェアが世界を飲み込みつつある)という論考を書いた米国トップティアVC、a16zのベンチャーキャピタリストMarc Andreessen(マーク・アンドリーセン)が最近あちこちで言っていることです。彼は起業家・投資家としてシリコンバレーのデジタル・イノベーションを最前列で実現してきた人物です。若い世代の人は知らないかもしれませんが、1994年にアンドリーセンらが創業したNetscape社は、1990年代半ばの商用ウェブブラウザ市場で圧倒的なシェアを持っていました。いまもネットを支えるJavaScriptやCookie、TSLといった基盤技術を作ったのもNetscapeです。
そんな人物が、2011年当時に誰もうまく言葉にできていなかった「スタートアップ」という勢いのある現象の本質をズバリと言い表したことで「Software is eating the world」という言葉は広く人口に膾炙することとなりました。私も含めてですが、テック業界の多くの人は基本的に、今もこのトレンドの中にあると考えているのではないでしょうか。
例えば、Amazonは本屋としてスタートしましたが、競争力の源泉はソフトウェアでした。ロジスティクスの効率化をする配送センターのロボットや専用端末を動かしているのは自社開発もしくは買収した企業のソフトウェアです。個人の嗜好に合わせたレコメンドをするのもソフトウェアと膨大なデータで、日々改善しながら運用しています。今となってはAmazonのアプローチは自明に思えるかもしれませんが、20年前は違いました。まだ2001年ごろには米国で有力な老舗書店だったBordersはAmazonに対して自社のオンラインビジネスを売り払ってしまいました。「オンライン書店は戦略的に重要でない」という理由で、です。これは自殺行為でした。10年後の2011年にBordersはチャプター11の経営再建手続きに入り、経営破綻しています。Amazonはその後、20年近くにわたって大規模なシステムを維持するために分散コンピューティングで多くのイノベーションを起こし、それをAWSというブランドの元に外販するにいたったことで、ほかのGoogleなどとともにクラウド時代を牽引しました。しかしクラウド関連技術は、年々急増する上に季節性の強い自分たちのトラフィックや、膨大な商品アイテムを扱うために生み出さざるを得ないものでした。Amazonが作った分散データベースは、それまでのOracleのようなデータベースとは全く性質の異なるものだったのです。
Netflixは人類初のグローバルな放送局兼コンテンツ制作スタジオのプラットフォームです。放送機器を自作する伝統的放送局はありませんが、Netflixはストリーミングやコンテンツ管理のインフラ技術をかなり自作してることで知られています。例えば、どのユーザーがどのコンテンツを好むかというリコメンドエンジンの改善では、2007年から2009年にかけて外部参加者を募ったコンペを開催。賞金1億円(100万ドル)を、Netflixのアルゴリズム精度を10%以上改善したチームに送ったことがありました。外部の力を借りていますが、自社の競争力の源泉を自社で所有していることには違いありません。NetflixはオープンソースのFreeBSDというサーバーOSを使っていますが、そのOS自体に手を入れてストリーミングを効率化するほどソフトウェア技術に力を入れています。今では信じられませんが、かつてストリーミングサービスは、なかなか再生が始まらなかったり、途中でクルクルと「読み込み中」のアイコンが回ったりしていたものです。Netflixは徹底してスムーズな再生を目指していて、実際ほかのサービスと比べてもUXは優れていたように思います。
AmazonやNetflixと同様に、2007年にスタートしたAirbnbがマリオットやヒルトン、インターコンチネンタルなど上位ホテルチェーンを全部足した部屋数より多くの宿泊先を旅行者に提供するようになったことや、Uber、DiDi、Grabなどが各地でタクシー産業のあり方を根底から変えてしまったことも「ソフトウェアが世界を飲み込む」象徴的な姿に思われました。
2015年の「シリコンバレーがやってくる」という手紙
その後に起こったのは、Fin-TechやEd-TechというxTechという多くのスタートアップが、デジタル技術を使って既存業界に新風を吹き込むというトレンドでした。また深層学習の画期的なブレイクスルーにより、AIの適用を待つ産業領域が注目され、2010年代半ばからはデータにも注目が集まるようになりました。これが2011年にアンドリーセンが言った「ソフトウェア」の位置付けを変えたように思います。「デジタル」とか「デジタル技術」というのは、ソフトウェアだけでなく、ネットワークやデータ、そしてそれを集めるセンサーなどを総称したアンブレラ・タームです。もはやアルゴリズムだけで差別化するのは難しくなりました。このこともDXという言葉が徐々に広く使われるに至った背景にあるのではないでしょうか。シリコンバレーでは今も「テック」という言葉で、ソフトウェアを中心としたIT業界を呼び習わしていますが、これは元々言葉としておかしかったのだと思います。自動車製造が非テクノロジーなわけがありません。
2015年になると、デジタルによるイノベーションの勢いに気づいた米国東海岸では、今度は「シリコンバレーがやって来る」という手紙に象徴される恐れが、伝統的企業で共有されるようになっていきました。上にリンクした手紙はJPモルガンのジェイミー・ダイモンCEOが公開した株主への手紙の中にある一節で、これも時代の空気を言い表したコピーとして広く認識されるに至りました。
金融は元々扱っているのが情報であり、IT化も早かったわけですが、それでもデジタル技術の差が競争力となるのであれば、借り物としてのデジタルしか使っていない伝統的な産業のリーダーたちが危機感を覚えたのは、もっともなことだと思います。
2020年、伝統的企業が主語になりDXが始まった
ここ3、4年は少し違うことが起こってきているように見えます。今後もデジタル技術が産業や組織を変革していくことは間違いありません。ただ、それをドライブする主体は誰なのか、という話を考えるとどうでしょうか。伝統的大企業が「主語」となって積極的にデジタル技術を自社に取り込み、一部には成功事例も出始めているという流れがDXという言葉が急速に広まっている背後にあるように思えます。
1990年代のデジタル革命の黎明期にいたのはIBMやMicrosoft、Oracleといったコンピューター産業のコアにいたプレイヤーたちでした。次に2000年代にクラウド時代を牽引したGAFAが台頭します。2010年代には、そのクラウドやオープンソースをベースとした新しいソフトウェア開発のベストプラクティスを使いこなし、外部から各産業を変革するxTechのスタートアップ、そしてユニコーンが次々と生まれました。
こうした変化を見て、米国の伝統的企業のリーダーたちは、Amazon対Bordersのように変化に遅れをとって死んでしまわないよう2010年代から様々な取り組みをしてきたように見えます。
その1つがスタートアップへの投資と買収です。
CVCによるスタートアップへの年間投資額は、2014年の179億ドルから2019年の571億ドルと5年で3倍以上になっています。少しデータが古いですが、すでに2018年時点でFortune 100企業の77%がVCへ出資し、52%がCVC投資をしていました。CVCで純粋に経済的リターンを求めるケースはまれで、提携による事業シナジーや、M&Aによる自社のデジタル変革の加速を狙いとした戦略投資が大半です。
DXを実現するために、大手企業でCDO(Chief Digital Officer)の役職を設置するのが流行り始めています。これは人材や組織の変革も、事業やオペレーションのデジタル化と両輪だということの現れでしょう。それを一気に進める方法としてスタートアップ企業を買収するのは米国でも日本でも事例が出始めています。今のところまだ、スタートアップ買収の主流はメガベンチャーが自社に足りないスタートアップをすくい取って時間を買うような「デジタル・デジタル」の組み合わせが多数派ですが、米国では2015年にスポーツブランドのアンダーアーマーやアディダスが立て続けにフィットネスアプリのスタートアップをそれぞれ数百億円で買収したあたりを皮切りにして、2016年にはユニリーバが日用品D2CのDollar Shave Clubを1,000億円規模で、そしてゼネラルモーターズが自動運転スタートアップのCRUISEを1,000億円強でそれぞれ買収するなど、伝統企業がスタートアップ企業によってDXを推進する「非デジタル・デジタル」の大型買収がでてきています。大きな成果に繋がったと言える事例かどうかは時間が経ってみて初めて分かることですが、この傾向は今後も続くでしょう。
2つめは、これまでならスタートアップがやってきたようなデジタルな施策を大企業が自ら実施するという動きです。例えばディズニーやナイキの事例があります。
ディズニーが2019年末に開始した自社の有料ストリーミングサービス「Disney+」は、開始からわずか半年で5,000万の加入者となるほどの勢いです。コンテンツがあるというだけで加入者を集められるのかという懐疑の声を吹き飛ばした形です。ナイキは2017年からD2Cへのシフトを始め、2019年にはD2C事業の売上が1.2兆円に達しています。D2Cは「ネット直販」の言い換えだと皮肉を言う人もいますが、ソーシャル・モバイルという新技術の台頭に合わせて発達したストーリーテリングやデータを生かしたマーケティング及び販売方法と捉えれば、これはDXそのものだと言えるでしょう。振り返ってみれば、ネット直販は単にそれまでの店舗販売の購買行動部分だけをウェブに置いただけのもので、過渡期的な形態だったのだと思います。
オペレーションのDXと、事業コアのDX
DXと一口にいっても、従来、紙やメールで行っていた業務を、もう少し進化したSaaSやITシステムで置き換えるという意味での「業務のDX」と、ナイキやディズニーのように事業コアをデジタル時代に合わせてスライドしてしまうという「事業のDX」の2つがあるように思われます。
現在の日本で良く聞くDXは前者の文脈が多いように見受けられます。確かに現代的SaaSの業務や分析のツールを採り入れて、それに合わせて組織文化やワークフロー、働き方改革を実現するだけでも効果は大きいと思います。しかし、本丸は事業コアのデジタルによる再定義ではないでしょうか。繰り返しますが、中長期的には全ての産業においてデジタル技術が得意な企業だけが生き残るのだと思います。2020年にメールやクラウドを使わない企業に競争力がないように、今後はデジタル技術で自分たちの組織や事業を動かしていない企業の存続は危うくなっていくのではないでしょうか。DXを推進するか、最初からデジタルの新興企業に市場を奪われるかのいずれかです。
既存の非デジタル企業がDXしていく道のりは、ITベンダーや外部コンサルタントによる変革や、スタートアップとの協業・買収によるもの、CDO設置による内部からの変革など、いろいろあり得るかと思います。いずれのケースでも、DXが中長期的視点に基づく社会の包括的デジタル化を指し示す言葉で、今までと違ってITの提供者側の論理ではなく各企業が主体的に取り組み始めたことを象徴している言葉であるのであれば、これは日本社会にとって前向きな話ではないでしょうか。