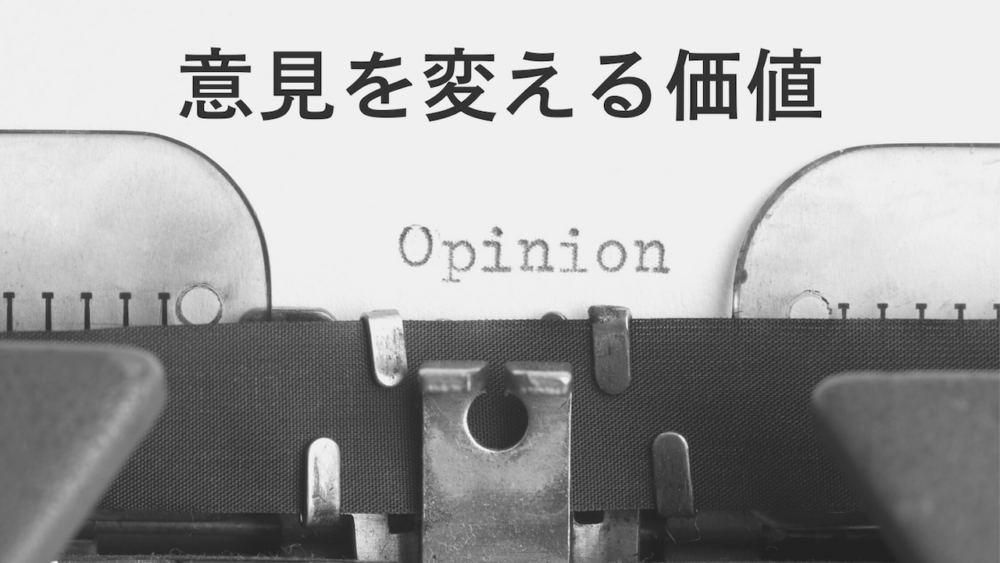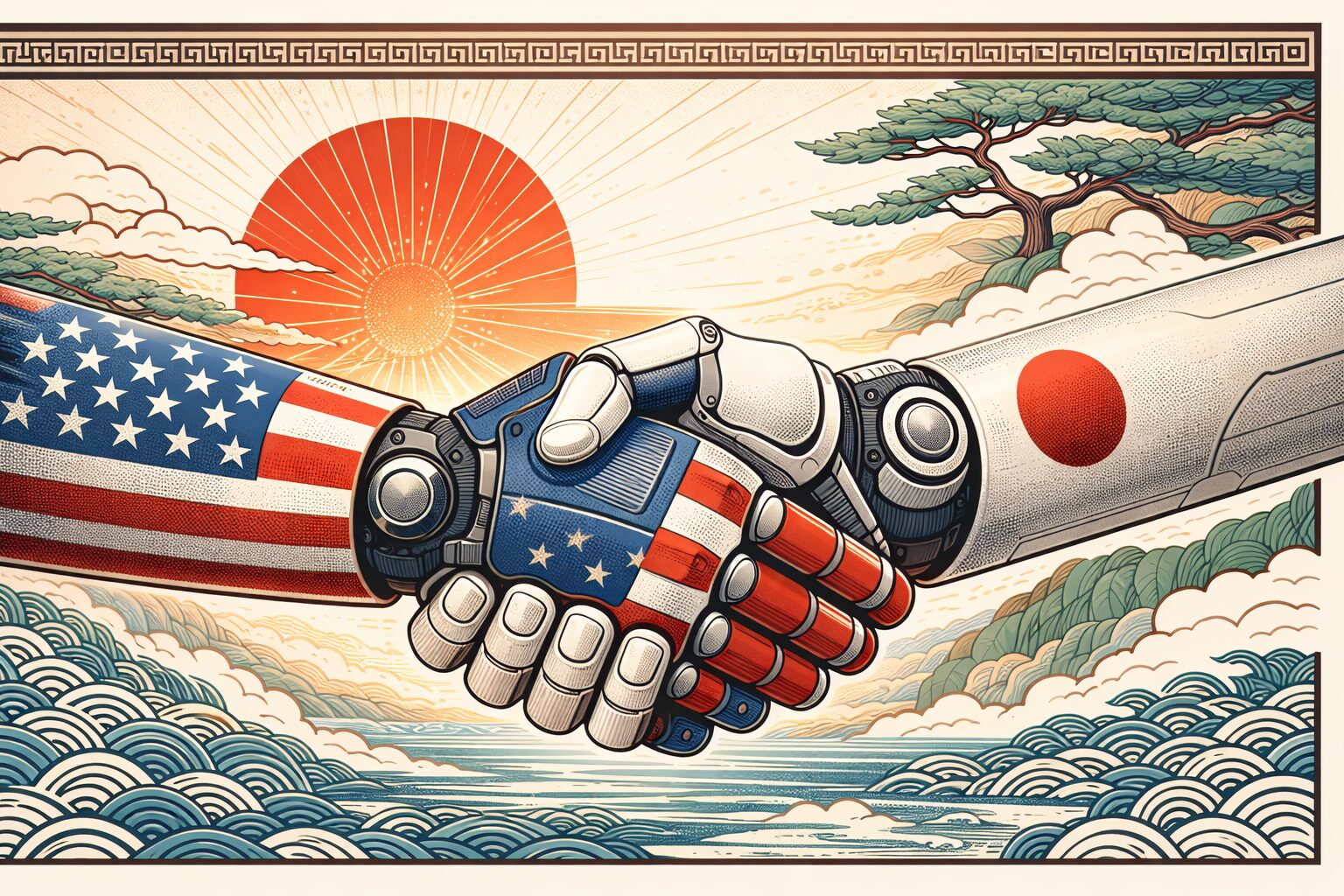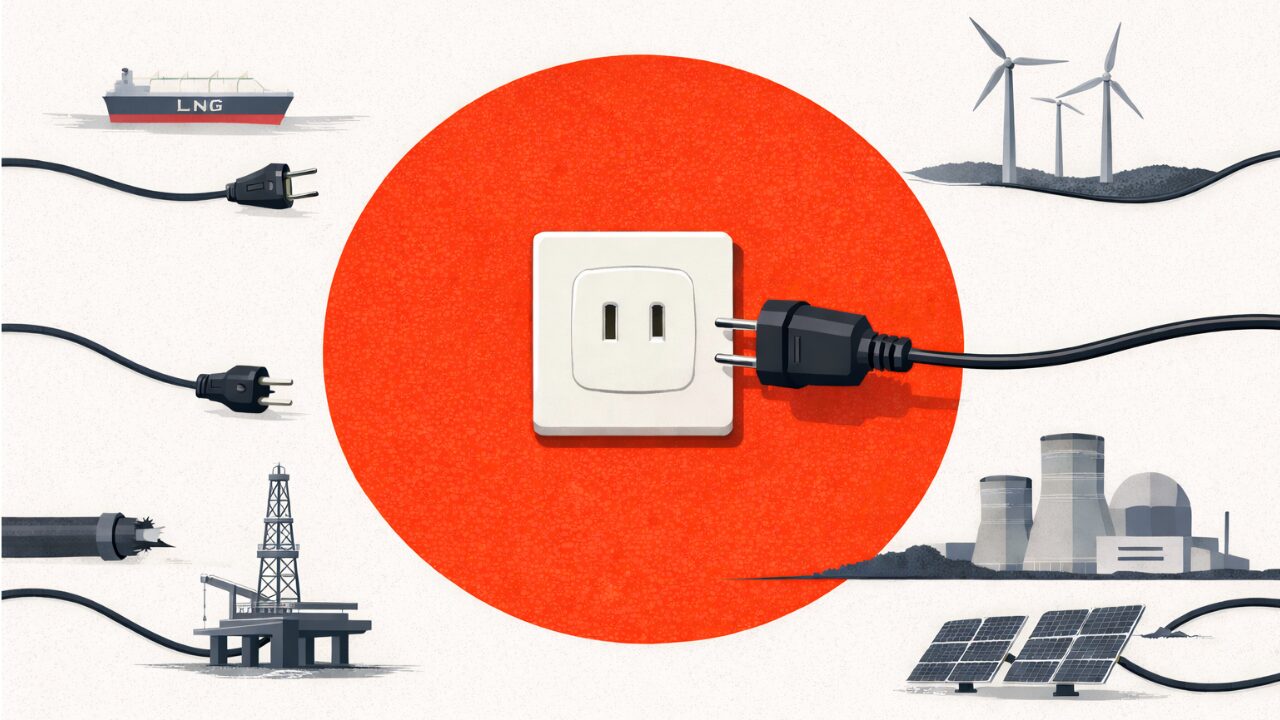2019年に邦訳も出ているのでご存知の方も多いかもしれませんが、iPhone誕生の過程を関係者らへのインタビューから詳細に描いた『THE ONE DEVICE ザ・ワン・デバイス』(ブライアン・マーチャント著)によれば、アップル社内で最初にiPhoneを構想したのはスティーブ・ジョブズではありませんでした。むしろジョブズは2004年頃まではスマホ市場参入には明確に反対していました。なんで、そんなものをアップルが作る必要があるんだ、と。
THE ONE DEVICEの原著出版時(2017年)にテック系メディアのThe Vergeに掲載された、かなり詳細な著書の引用を読んで分かるのは、iPodやiPhone誕生の場面場面で、スティーブ・ジョブズが確固たるビジョンを持ってプロダクトを生み出したということではなかったということです。iPodはリリース直後は連携するソフトウェアのiTunesがMacでしか動きませんでした。このためiPodはMacと一緒でしか使う意味がなく、結果として音楽プレイヤー市場でiPodは鳴かず飛ばず。Windows版iTunesは「オレが死なない限り絶対に出さない」と言っていたジョブズを説得したのはトニー・ファデルでした(トニー・ファデルはiPod/iPhoneの立役者。後にNESTを共同創業して、Googleに32億ドルで売却しています)。
違う意見で先走るメンバーと、自説を変えられるトップ
興味深いのはWindows版iTunesについて、ジョブズが強く反対していたときに、すでにソフトウェア自体は、こっそり作り始めて準備をしていたというエピソードです。iPhoneも同様で、ジョブズが最終的に折れて「わかった。やるべきだと思う」と2004年に電話越しにベテラン・エンジニアのマイク・ベルに対して言うまでにも、タッチUIの開発プロジェクト自体はアップル社内にあり、多くのエンジニアやボードメンバーがジョブズに「電話を作るべき」と説得しようとしていたといいます。
ここで大事なのは、「こんなの売れるかっ」とジョブズに罵られながらも才能のあるエンジニアたちがプロトタイプを見せてジョブズを説得していったということと、最終的に自説を180度転換してジョブズがゴーサインを出したということだと思います。Androidという競合が出たりスマホ市場が立ち上がる3〜4年前のことです。
組織トップのジョブズを始め、会社として意見を変えられたことがアップルとBlackBerryの命運を分けたということです。メール端末として一世を風靡したBlackBerryは最後まで物理キーボードにこだわり過ぎ、ガラケーやフィーチャーフォンとともに消えていきました。
意見を変えることの価値
アップルとBlackBerryの違いについての上記の視点を、私はアダム・グラントの近著『Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know』で知りました。意見を変えることや、自分に何が分かっていないか知るメタ認知には一般に思われているよりも価値があるということを、多くのエピソードや研究成果を引用しながら紹介した本です。
この著書で紹介されている研究の中で、最もスタートアップの文脈で興味深いものについては、以前、以下の記事でも紹介しました。
ピボットで1年後売上は約50倍の伸び、イタリアの116社の実験で判明 | Coral Capital
結局のところ、事実や観察、それに基づくロジックや数理的思考によって、いつでも意見を変えるという態度こそがビジネスでも肝要だということではないでしょうか。
ほとんどの人は意見を変えません。Twitter上で「確かに、おっしゃるとおりですね。これまで間違った考えを持っていました。今日から考えを変えました。教えてくださってありがとうございました」というツイートを見ることなど、まずありません。現実の会話でも、ほとんどありません。特に政治的な意見については、そうです。
一方で、常に異なる意見に対して開かれた態度を持ち、いつでも変える気でいる人というのは少数ながらいます。意見を変えることが経済的インセンティブに結びつきやすい投資家や、どんな意見も反証されうる仮説に過ぎないと考える科学者などに、そうしたタイプが多いように感じています。
アダム・グラントは著書の中で、自分の意見を疑ったり、別の意見を精査する手間を惜しむのは知的怠慢によると指摘しています。そして私たちは3つの職業タイプに分類される態度を取るようになるのだ、と。その3つというのは、①自分が信じることを伝道するだけの「伝道者」か、②他者の意見の欠陥をあげつらう「検察官」か、③周囲から支援・賛同を得ることだけを目的に戦う「政治家」の3つです。自分でも他人でも、誰かが自説に過度にこだわっているとき、確かにこうした形容がピッタリと思えることがあります。
試験の最後の1分で回答を変えるべきか?
自分の意見について、変えるべきかどうか迷うことは日常的にあります。起業家なら仮説検証において、どの意見が正しくて、どの意見を棄却すべきかは常に悩むでしょう。
「意見を変えるか、変えないか」は個別の問題であって、問いと状況次第だと考えるのが普通だと思います。でも、アダム・グラントがベストセラー作家なのは「『意見を変えるか、変えないか』ということに関する意見」を少し変えるように迫る、そんなメタなアドバイスをしたりするからではないかと思うのです。どうやら私たちには「意見を変えない」ことを尊重しすぎる傾向があるようです。
以下の研究成果を知って、私の中で「意見を変えることに関する意見」は少し変わりました。その研究とは学校の試験に関するもので、いったん書いた問題への答えを後から思い直して変えることについて、です。
試験の残り時間が1分を切ったとき、答案用紙全体を振り返って、何かの回答を変えようか迷った経験は多くの人にあるかと思います。「いや、これはAじゃなくて、やっぱりBだ。Bに変えよう。いやいや……、最初にAだと考えたのはこういう理由で、それはそれで正しく思える……。やっぱり変えるべきではない」という状況です。
イリノイ大学の約1,500人の学生を対象に、中間試験を分析した研究によれば「変更された回答」について言えば、
- 不正解→正解(51%)
- 正解→不正解(25%)
- 不正解→不正解(23%)
となったといいます。つまり変更した回答に関して言えば、そのことで点数が上がっているわけです。ということは、もっと回答を変えるのが正しい態度だということです。この研究結果は、変えるべきときに変えていない現実を示しています。別の言い方をすると「悩んだときは後から変える」という回数を少し多めにするのが正しいアプローチだということです。
なぜ、こんな変なことが起こるかというと「変えた結果、間違えた」というときの(想像上の)後悔は、「変えた結果、正解だった」という喜びに比べて非対称に大きいため、変えるべきときに変えない心理傾向があるからではないでしょうか。心理学の研究者らは、これを「最初の直感の錯誤」(first instinct fallacy)と名付けたそうです。「第一印象バイアス」とでも訳したほうがわかりやすいかもしれません。
個別の意見や議論は是々非々で考えるべきですが、「意見を変える」ということについての意見については、アダム・グラントが指摘する通り、再考すべきことがあるのかもしれません。