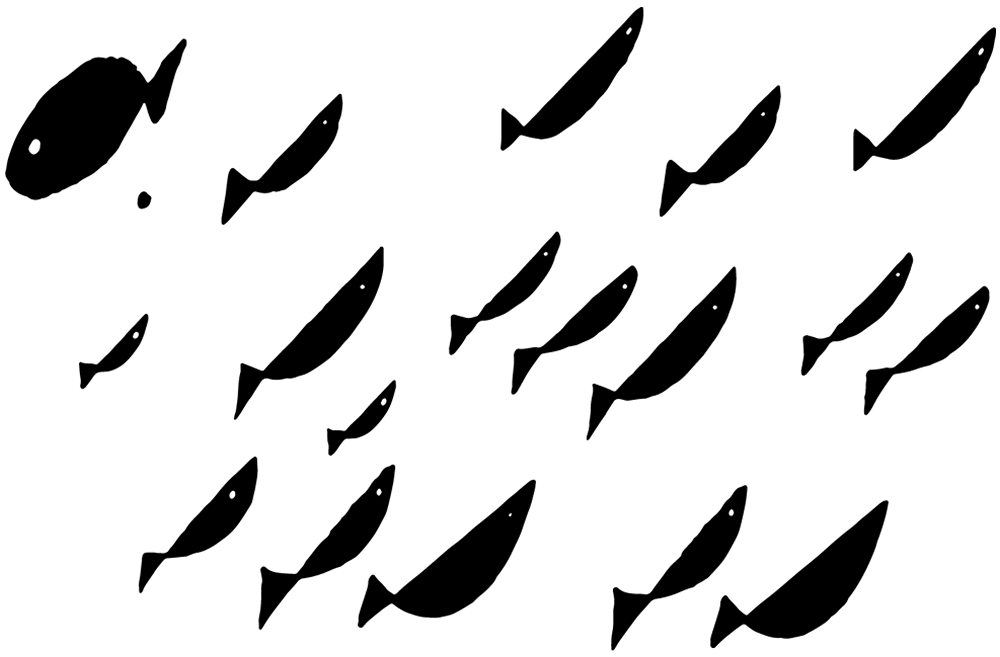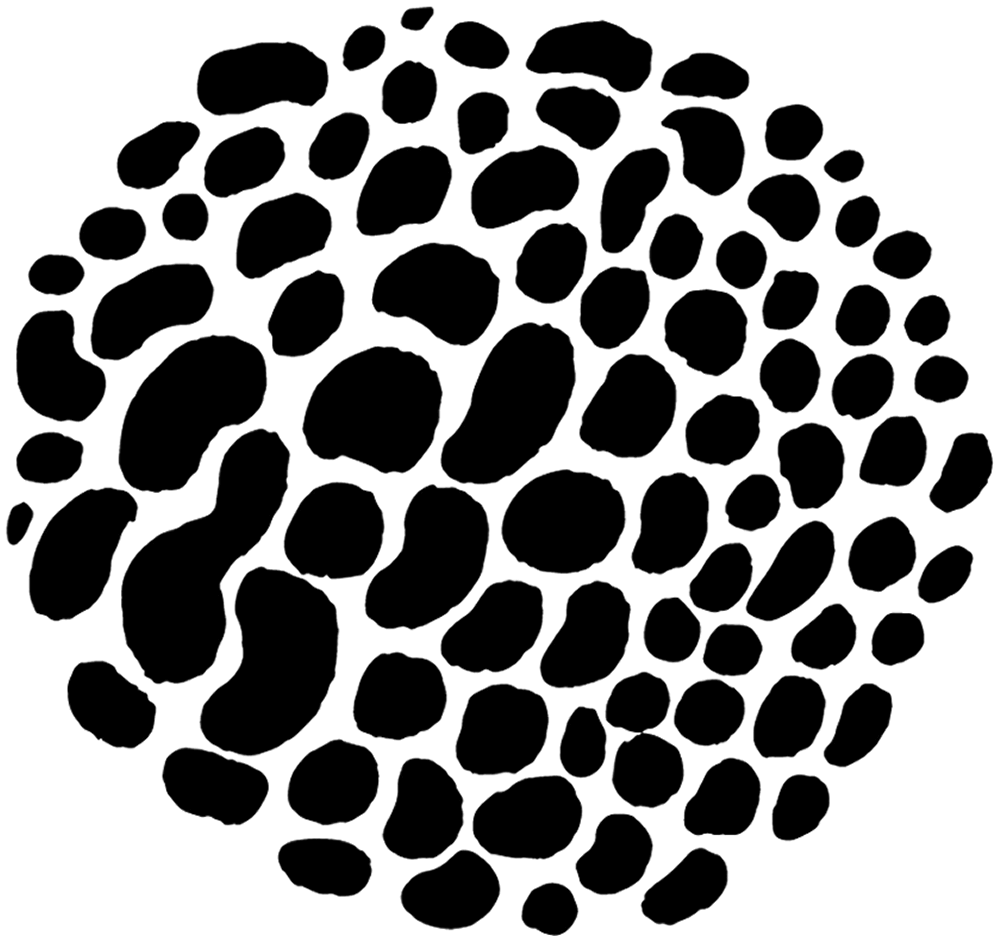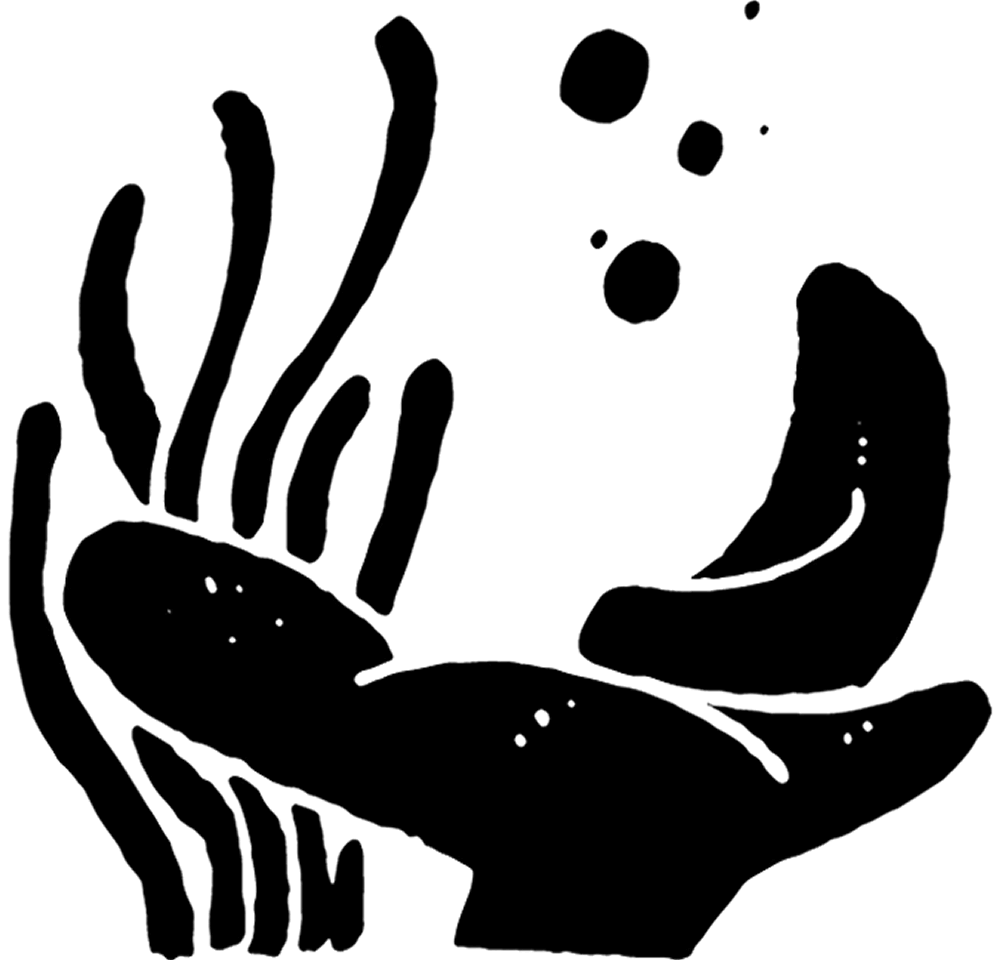米国では一般的にスタートアップの株式は、付与されてから4年間のベスティング期間(権利確定期間)を設けるのが「標準」とされています。しかし、なぜ4年なのでしょうか。なぜ6年や、2年、もしくは10年などではないのでしょうか。
4年のベスティング期間がスタートアップ界でスタンダードとなったのは、主に歴史的および実用的な理由によるものです。当初、この4年という期間は、米国で企業が上場するまでにかかる一般的な期間と一致していました。また、かつてVCは(常にではありませんが)多くの場合、起業家が必ずしも会社を経営し続けるわけではなく、プロの経営陣が雇われることを想定してスタートアップに投資していました。雇われた経営陣には、インセンティブとして株式が付与され、1970年代から1990年代の終わり頃までこの慣習は続きました。つまり、ベスティング期間を4年に設定すれば、IPOなどの「流動性イベント(株式を現金化できるイベント)」が発生する頃には、経営幹部がすべての株式持分の権利を行使できるようになっていたのです。実際、AmazonやNetscape、Yahoo!はいずれも3年以内に上場しています。日本でも、サイバーエージェントが24ヶ月、楽天が38ヶ月で上場しています。このようにスタートアップが短期間で上場していたため、4年間のベスティングスケジュールが適切とされていたのです。
このトレンドは1990年代の後半にドットコムバブルが崩壊するまで続きました。バブルの崩壊により、上場企業であることのリスクに対する人々の認識は大きく変わりました。加えて、2002年に施行されたSOX法により、上場に伴うコストや手間が増え、多くの企業がより大きな規模になるまで上場を遅らせるようになりました。この規制とドットコムバブルの崩壊が重なった結果、企業は上場に対してより慎重なアプローチを取るようになったのです。さらに、短期的視点に偏りがちな外部からのCEOを雇うのではなく、起業家自身が経営を主導するスタイルへのシフトも当時進んでいました。このトレンドの象徴的な例が、Facebookのマーク・ザッカーバーグです。Facebookではザッカーバーグが戦略やプロダクトに集中し、業務運営はシェリル・サンドバーグに委任していました。このような経営スタイルにより、起業家はより長く会社に携わることができ、長期的な視野で会社を成長させることが可能になったのです。
並行して、プライベートマーケットで調達できる資金も大幅に増加しました。その結果、スタートアップは上場を急がずとも、未上場のまま成長に必要な資金を調達できるようになりました。また、プライベートマーケットへの資金流入が増えたことで、VCファンドの規模が拡大し、上場市場の投資家もプライベートマーケットの資金調達ラウンドに参加するようになりました。これにより、上場市場とプライベートマーケットの境界線も曖昧になってきています。
日本の場合、米国と比較するとそこまでは厳しくはないため、今でもスタートアップが比較的早期に上場することが可能です。とはいえ、米国同様にVCファンドの規模が拡大し、プライベートマーケットへの投資が増加しているため、日本でもイグジットまでの期間が長くなりつつあります。一方で、米国と違い、日本のスタートアップではこれまで社員に株式を付与することがあまり一般的ではありませんでした。しかし、最近になって日本のスタートアップでも株式インセンティブがようやく普及し始め、ベスティング期間について再考する必要が出てきています。会社を十分な規模まで成長させるのに7~12年かかるとして、標準的な4年のベスティング期間は果たして適切なのか、改めて考えなければなりません。
また、米国ではスタートアップの上場が遅れる傾向が進む中、セカンダリーマーケットが活性化し、アーリーステージの投資家や社員がレイターステージの投資家に持分を売却できるようになりました。その結果、株主構成の変動は大きくなり、ステークホルダーはIPO前でも株式を現金化することが可能になっています。日本でも、株式の流動性に関して同様の傾向が見られます。国内のセカンダリーマーケットの重要性はますます高まっており、今後大きな成長が期待できるでしょう。
4年のベスティング期間は、数十年前に形成された業界の常識に基づいたものです。しかし、それ以来、業界の状況は変わり、スタートアップがIPOなどの流動性イベントに到達するまでの期間も長くなっています。私たちは今、ベスティング期間や、セカンダリー取引全般に対する認識をアップデートするべき時期に来ているのかもしれません。
Founding Partner & CEO @ Coral Capital