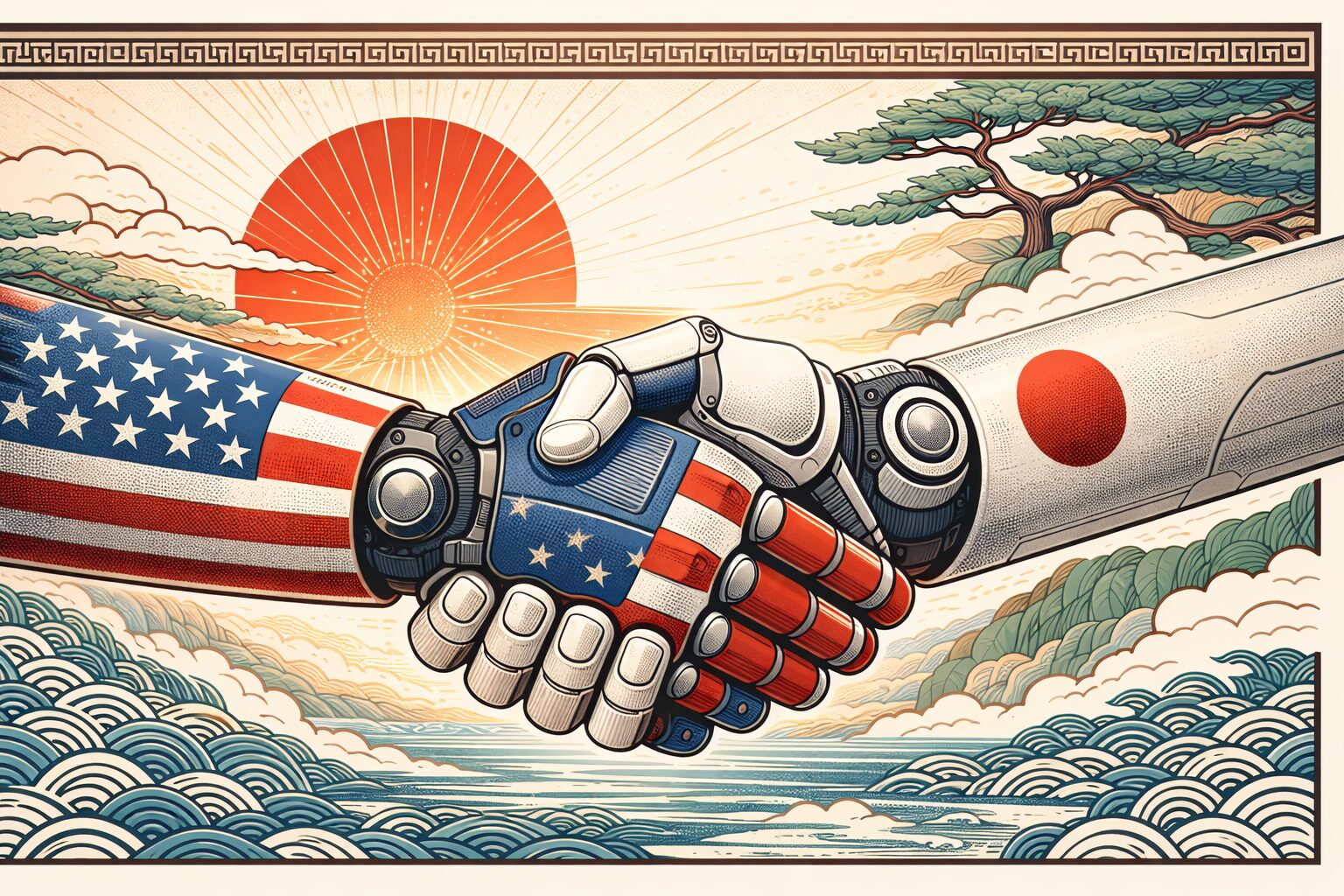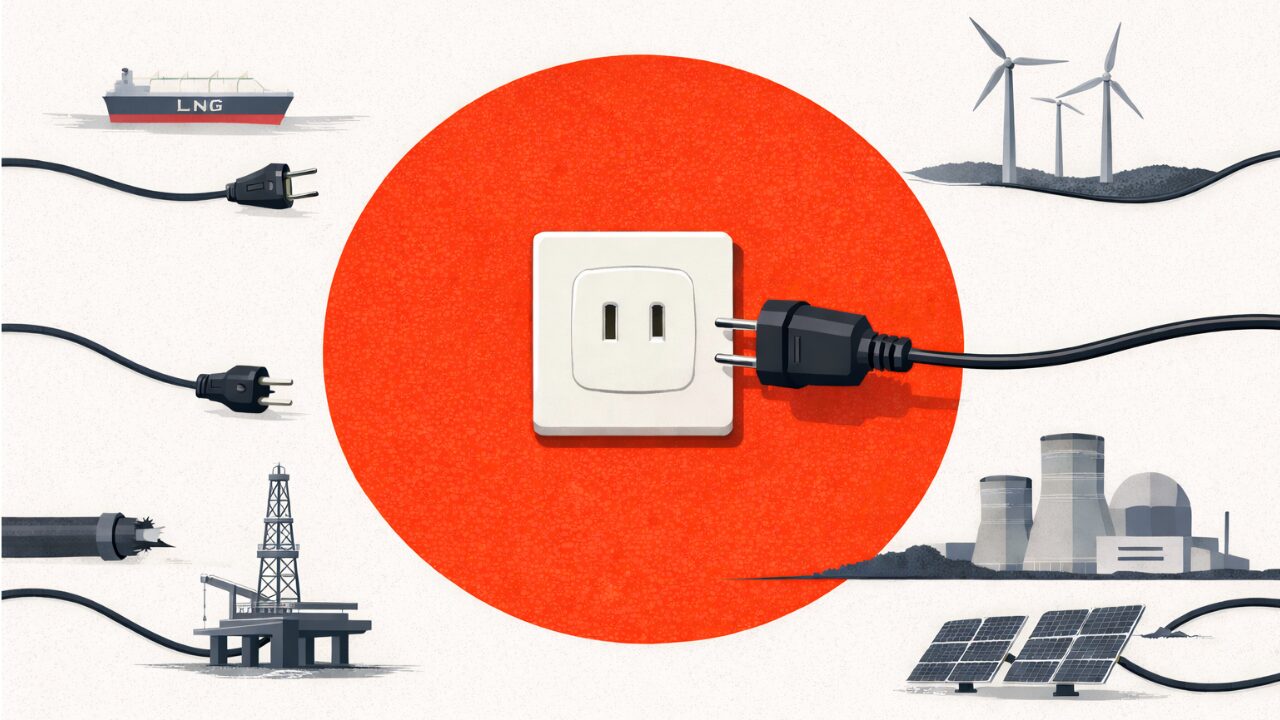インドがIT大国であることは多くの人が知っているかもしれません。
約30年前のインド―。深刻化していた財政危機を打開するために1991年から断行された関税引き下げや外資規制の緩和など経済自由化に流れにより、外資のインドへの直接投資は、ものの数年で3倍以上に。その後はGDPが30年で10倍以上となり、今やインドは世界5位の経済大国となっています。この自由化の流れの中で、欧米IT企業の進出や業務プロセスのアウトソーシング、オフショア開発が一大潮流となったことは、私たち日本人も良く知るところです。インドブランドエクイティ財団によれば、今やインド経済全体のうちIT産業が9.3%を占めるほか、世界全体の「IT外注市場」で見たときインドのシェアは56%にも及ぶといいます。
英語を準公用語とすることから欧米との人的な行き来も盛んです。
GoogleやMicrosoft、IBM、Twitter、Adobeのように米国テック企業の多くでインド出身のCEOが活躍するほか、米国で学んだりキャリアを積んだテック系インド人材が帰国してスタートアップを起業したり投資する流れが加速。ユニコーン企業数が2022年に100社を超えるなど活況を呈しています。欧米のビッグテックや通信企業は、どこもインドに開発拠点を持っています。
そして、今やインドにソフトウェアの開発拠点を開設するのは米中や東南アジアのスタートアップでも同じです。
であれば、なぜ日本企業も、それをやらないのか?
楽天など一部を除いて日本のテック企業がインドにR&D開発拠点を開設する事例は多くありません。シリコンバレーやインドへの赴任経験があり『激動するインドIT業界 バンガロールにいれば世界の動きがよく見える』などの著作もある元ソニーの武鑓行雄氏はTECHBLITZのイベント登壇時に「インドは、2000年代初頭は下請け的な仕事でしたが、この10年でハイエンドな技術開発、製品開発ができるようになってきている」「取引先は圧倒的にアメリカで62%。そのあとイギリス、ヨーロッパです。日本とは1%以下」と話をしています。
こうした背景があるなか、インドに本格的に拠点を構えるテック企業が日本でも出てきました。新興のSaaS企業を代表する1社であるラクスルは2020年7月、インドに開発拠点を開設。単にエンジニアリソースを確保する外注先などではなく、最新SaaSプロダクトでは「技術チームはインド」「プロダクトやセールスチームは日本」という体制に。従来にない新しい体制と、そのオペレーションを回す仕組みを確立したと言います。
Coral Capitalではラクスル創業者で代表取締役社長CEOの松本恭攝さんと、インド・ベンガルールに開設したラクスル100%子会社となるインド拠点(RAKSUL INDIA PRIVATE LIMITED)の代表を務めるサンジェイ・ラジャセカール(Sanjay Rajasekhar)さんに話を聞きました。
(聞き手:Coral Capital創業パートナーCEO James Riney /同パートナー兼編集長 西村賢)
マクロで見て日本でのエンジニア採用には限界がある
ジェームズ:どういう経緯でインド拠点を開設することになったのですか?
松本:そもそもインド拠点開設の取り組みは2019年頃に始めました。エンジニアが採用できないという課題が大きくなっていたんです。弊社取締役CTOの泉(泉雄介氏)とは、日本だけに絞っていてはエンジニア採用が継続できないという話をしていました。
今は日本でもVCマネーが増えていますよね。海外からの投資もありますし、独立系VCもファンド規模が大きくなっています。それでスタートアップの数は増えているのに、エンジニアの数は増えていません。日本の大学では、ハーバードやスタンフォードのようにコンピューターサイエンスを教えておらず、卒業生が増えてもいません。だから人材の量も限定的です。
結果として、平均的なスタートアップは採用に非常に苦労しているわけですが、この状況がすぐに改善するとは考えられません。マクロで見れば日本のエンジニア不足の状況は厳しいです。
だから、何かマクロの条件を変える必要があったんです。
それでグローバルの市場調査をしたんですね。例えば、イギリス、ドイツ、中国、インド、ベトナムなどです。どのくらいの数の大学でコンピュータ・サイエンス教育をやっているかはもちろん、国ごとのGitHubのアカウント数なども調べました。
ジェームズ:国別GitHubアカウント数の調査というのは初めて聞きました、おもしろいですね。
松本:ほかにも、ソフトウェアエンジニアの平均給与をGlassdoorで調べて、インドが良いという結論になりました。
こうした調査に加えて、シンガポールや香港の経営者の友人たちを訪ねて、すでにユニコーンになった彼らにエンジニア組織をどうしているか聞いたんですね。そうしたらインドにR&Dセンターを設立したんだ、という答えが返ってきたんです。インドにR&Dセンターを設置していたのは、当時の日本では楽天くらいでした。
でも、アメリカでもシンガポールでも中国でも、ユニコーン企業はインドに開発拠点を持っていますよね。なぜ私たち日本だけはインドに行かないのでしょう? シリコンバレーのテック企業の経営メンバーを見ても、例えばGoogleやMicrosoftのCEOはインド人ですよね。
ジェームズ:日本企業はベトナムに開発拠点を持つことが多いですよね。
松本:ええ、周囲のテック系起業家に聞いても、みんな「ベトナムは親日であるものの、インドは文化が全く違うから」と言っていました。確かに、ベトナムの方は日本のマネジメントに合わせる柔軟さがあるので、日本の経営者にとっては管理がしやすいということはあるかもしれません。
ただ、ベトナムとインドを比べると、ベトナムのエンジニアではジュニアメンバーが多いんですね。グローバルのハブかどうかという点でもインドと違います。いまは少しずつ変わりつつありますが、ベトナムでは大学を出た人材がユニットとして開発はしていても、メンバーを牽引するリーダーシップがないために大規模なR&Dセンターがありません。
一方、インド人テック人材はシリコンバレーのテックジャイアントや大企業で働いた経験があり、マネジメント経験のある人材も豊富です。それで私たちはインドに行くことを決めたんです。目的はアウトソーシングなどではなく、リーダーシップを探しに行くことでした。そこで出会ったのがサンジェイでした。
アウトソースではなく開発の中心を担う拠点に
西村:サンジェイさんはラクスル・インドの拠点長として組織の立ち上げから関わっていますが、そもそも松本さんの出会いはどんな感じだったんですか?
サンジェイ:もう2年以上前のことですが、ラクスルCEOの松本さんとCTOの泉さんがインドを訪問していたときに共通の知り合いを通して、飛行機のフライトの直前に空き時間に少しだけ面談したんです。ちょっとご挨拶というようなものです。ところが、まるまる2時間も話すことになって、2人は危うくフライトを逃すところでした。すぐに話に夢中になって、これはさらに深堀りして話す必要があると3人とも感じたんです。
西村:サンジェイさんは過去20年間、Honeywell、Dell EMC、Nortel Networksといった多国籍企業でエンジニアチームの組成や変革に携わって来られた経歴があります。エンジニア組織の構成メンバーも各国に散らばっていたわけですよね。そうした経歴から見て、日本企業は異質ではなかったですか? リーダーとしてインド拠点立ち上げを引き受けた理由は?
サンジェイ:海外拠点をオフショアのような立ち位置にせず、最初から非常にインパクトのあるプロダクトづくりができる仕事ができるオフィスにしようとしていることに感銘を受けたんです。インドが提供する人材や技術にとても敬意を払っていることも分かりました。
われわれはラクスルのインド拠点を、単なる「オフショア開発拠点」ではなく「ラクスルの未来を共に創造していく開発拠点」と位置づけています。インドにいるトップクラスのエンジニア人材にとって魅力的な、高水準の技術と目的のある仕事を提供することが拠点設立の狙いでもあります。もちろんラクスルのビジネスの成功とスケールアップが目的ですが、それにとどまらず、長期的には日本のベンチャー企業が「グローバル化を受け入れてさらなる成長を遂げる」成功モデルとなることを目指したいと思っています。
西村:迷いはなかったですか?
サンジェイ:パンデミックの真っ只中に、インド拠点を立ち上げるというのは、ラクスルの経営陣にとって非常に大胆な決断だったと思います。新しい国、馴染みのない文化、新しいリーダー、パンデミック、リモートワーク、ゼロ・イチの挑戦……。これはパッションと胆力がなければ、できないことです。
一方、 私の立場から見ても、これは思い切りが必要な決断でした。ミッション・インポッシブルと言ってもいいかもしれません。しかし、リーダーとして目的意識に訴えかけるものがあったのです。だからこそ、私は初日から全力投球でした。
日本とインドでは「シニア」の意味が違う
ジェームズ:日本とインドでは経営スタイルが違って戸惑いはありませんでしたか?
松本:ええ、インドの人たちは米国流のマネジメントに慣れています。これは日本流のマネジメントと全く違います。
日本では明確に定義されたジョブ・ディスクリプションがありませんし、パフォーマンス評価のための数字も明確に決まっておらず、「すり合わせ」が重要です。いわゆる「ハイコンテクスト」なマネジメントです。これがインド、米国のローコンテクストなスタイルの人たちと摩擦をひき起こすんですね。
サンジェイ:これまで2年が経過してみて、かなりの発見がありましたね。テック業界でいう「シニア」「ジュニア」は地域によって非常に異なる意味を持っています。インドの技術者の例を挙げましょう。シニア・エンジニアとは、より複雑なアーキテクチャのシステム設計を引き受けることになります。
エンジニアは何かに特化するものです。例えばスケーラビリティやパフォーマンスに特化したエンジニアがいます。あるいはUIなど非機能的要件などもそうです。こうしたものをプロダクトに組み込む仕事は、複雑さの指数がぐっと高くなりますよね? より多くのコードを書くのではなく、シニアレベルで「10倍上に行く」というのは専門性が高くなることで、10倍以上のコードを書くということではありません。
ところが日本は少し違います。
新プロダクトを開発して、それをできるだけ早く市場に投入するというとき、日本側が期待していたのは、シニア・エンジニアたちが腕まくりをして、プロダクトローンチを早めるためにできる、あらゆることについて片っ端から手を着けることでした。シニア・エンジニアに望んでいるのは特化した尖った専門性ではなく、全体像を把握することだったのです。そのことを理解してからは、橋渡しをするようになりました。
日本の組織のシニア・エンジニアなら「AとBとCとDとEが重要だ」というようなことをいちいち言う必要はなくて、すべて当たり前のことなんですね。逆にインドでは他の人の仕事の領域に口出ししたくないんです。自分は、自分の仕事を完璧にこなしたいと思っているんです。
日本では誰が何をすべきかについて、みんなが正確に知っていて、説明や指示、文書化、役割分割といった対応を必要とせず、いつ何をすればいいのか、すべてわかっているのです。仕事や役割の垣根を越えて、人がうまく一緒に仕事としていることに驚かされました。お互いに衝突することなく、驚くほど重なり合った状態でうまくやっていけている。そういうハイコンテクストな仕事の進め方なんですね。
でも、それは日本以外では当然の能力なんかではないんですね。少なくともインドでは違います。日本では何も文書化されておらず、誰も何も言いませんが、インドだと職務の分離、明確な役割と責任の定義、明確に示された期待というものがあります。
「開発はインド、セールスは日本」多国籍チーム運営の秘訣は?
西村:具体的にインド拠点と日本側はどうやって協調して動いてるのですか?
松本:弊社では、祖業である印刷の「ラクスル」、それに続く物流の「ハコベル」、テレビCMの「ノバセル」と立ち上げてきて、今はITデバイスとSaaSの統合管理クラウド「ジョーシス」を2021年9月にローンチして立ち上げ中です。
ノバセルを開発した頃にはベトナム拠点で40人ほどエンジニアがいました。ハコベルはインド。海外拠点を徐々に拡大した形ですね。
ジョーシスに関しては、開発の中心はインドです。ジョーシスでは「技術チーム」「プロダクトチーム」「セールスチーム」と大きく3つのチームに分けているのですが、技術チームは20人規模で、その9割がインドにいるインド人です。
西村:ユーザー企業は日本ですよね?どうやって仕様の調整、開発の優先順位付けをやっているのですか?
松本:ええ、顧客は今のところ日本です。セールスは3人のフルタイムと、10人のパートタイムメンバーがいます。3つのチームは四半期ごとにゴール設定やKPIを明確にし、ジョブディスクリプションも定義しています。プロダクトチームは日本とインドのハイブリッドです。このチームがコラボレーションチームとしてローコンテクスで透明性の高いやり取りを担保するようにしています。
リーダーシップレベルでは、インドの技術チームと、日本のセールスチームが議題を持ち寄って議論しています。意思決定をするのは日本でもインドでもなく、両グループのコラボレーションによって、です。
また、ここで決定した事項については、誰もがその内容をNotionなどの議事録から知ることができ、会社がどういう方向に行こうとしているのか、どういう状態なのか分かるようにしています。
Zoomは同時通訳、SlackはDeepLボットで意思疎通
ジェームズ:セールスとエンジニアは同じ国にいてもコンフリクトがあるものですが(笑)、どうやって解決しているのでしょうか?
サンジェイ:ええ、その通り。もし何か意見の衝突があったら、リーダーシップがコミュニケーションする場以外でも、週次のトランスペアレンシー・ミーティングで話せます。だからインドのエンジニアチームが取り組む課題というのは、常にプロダクトとセールスの両方から100%の合意が取れた状態のものです。優先順位が高くない開発に着手することはありません。
ミーティングは日本語なのか英語なのか、バイリンガルなのかすべて事前に決められています。バイリンガルの場合には、Zoom越しに同時通訳者が参加します。われわれの通訳者は非常に優秀で、日本語をどんどん英語にしてくれるので会議内容も完全に理解できます。通訳者不在の場合にはリーダーの誰かがまとめて通訳するようにしています。SlackではAI翻訳のDeepLボットを活用していますね。
松本:ミーティングの際には事前にアジェンダを文書化して、参加者が事前に読むようにしていて、これもDeepLで誰もが理解できるようにしています。
英語力向上という意味だと、フルタイムの英語講師を採用しているほか、ケンブリッジ英語検定を取り入れています。私自身も英語レッスンをやってるんですよ。大学に入ったときのTOEICスコアは340点で、今もあんまり英語が得意じゃないので(笑)
ジェームズ:今はぜんぜん英語うまいじゃないですか! ラクスルでは会社全体で英語を必須とする楽天のような「Englishnization」をやっていますか?
サンジェイ:英語力は大事で、特にジョーシスでは面談に私が参加していて、英語が話せるかを見ています。でも弊社で言えば、Englishniazationはうまく行かないと思っています。なぜかと言うとプロダクトは日本市場で使われるものだからです。英語と日本語のどこか中間の場所を見つけないといけません。
例えばラクスルの取り組みでユニークなのは、フルタイムでバイリンガルのコーディネーターがいることです。UXデザインやダイヤグラムなどがあったとき、そこに含まれる日本語をすぐに英語に翻訳してくれます。そのコーディネーターは日本人で、最近インド人と結婚してインドに住んでいる女性ですね。
激化するインドで人材獲得競争にどうか勝つか
ジェームズ:インドの人材獲得競争は厳しくなっていませんか?
サンジェイ:パンデミックの影響もあって過去2年は加熱しています。 面接を受けるほとんどの人が、複数の企業からオファーを受けているか、そうでなければ、すぐに複数のオファーを受けることになります。人材獲得では、大企業、外資系企業、スタートアップ企業など、あらゆる企業と常に競争しているわけです。インド人にとっては、もはや仕事を得られるかどうかの問題ではないのです。
そんなことより仕事の魅力が重要なのです。ビジネスの性質、会社の文化、リーダーシップの魅力、どんな技術を使っているか、あるいは個人的な成長が期待できるか、将来性はあるか、そしてもちろん福利厚生など、これらがすべての会社選びのときの意思決定のパラメーターなんです。
だからラクスルでも人材の見極めと同時にアトラクトを並行してやっています。ラクスルは多くの日本の伝統的大手企業と違ってシリコンバレー式のDNAを持ったスタートアップで、優秀な候補者が関心を持つ多様性などについて伝えています。ラクスルの「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる(Better Systems, Better World)」というミッション・ステートメントは、インドで優秀な候補者を引きつける魅力がありますね。
インドのエンジニアなら、欧米企業のインド拠点で仕事をしたり、知り合いの話で見聞きした経験があるものです。1980年代後半からありますからね。一方、ラクスルが新しいのは、シリコンバレーと日本という2つの世界のいいとこ取りをしたような独自の資質や価値観を持っていて、かつインドと協働しているるところです。これはとてもユニークな点だと思います。
海外のエコシステムに学んでアップデートしよう
西村:日本のテック系起業家にメッセージはありますか?
松本:私がインドに開発拠点を開設したというと驚く創業者も少なくありません。でも、シリコンバレー企業でも中国企業でも、みんなインドに拠点を設置していますし、GoJekやGrabといった東南アジアのスタートアップも、創業したその日からインド拠点をスタートさせています。そういうのを聞いていると、なぜ日本のスタートアップは、そういうことをやってないのだろうと思うようになったんです。
西村:今はメルカリが2022年5月にインド開発拠点を設立したり、マネーフォワードがエンジニア組織の英語公用語化を進めるなど風向きは変わりつつありますが、まだ一部という印象ですよね。
松本:シリコンバレーや中国のスタートアップのエコシステム、アジアのエコシステムを訪ねて、そこから学ぶことで、われわれはビジネスをアップデートできます。マネジメントスタイルやグロースハックなどです。そうやって十分に刺激を受けてから、意思決定の方法など、自分たちのやり方を変えていけばいいのではないかと思うのですよね。