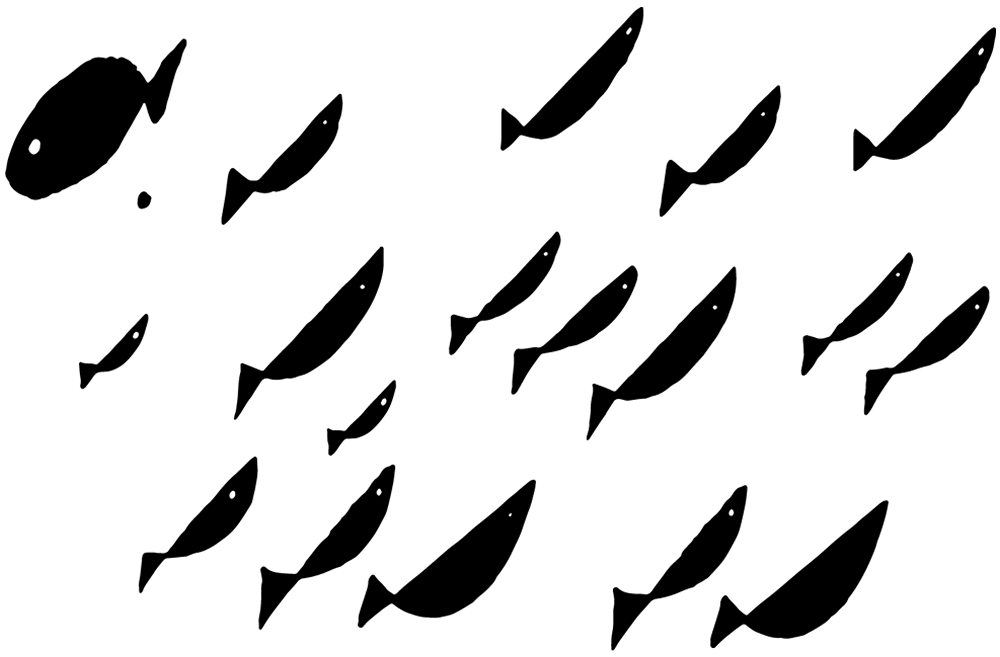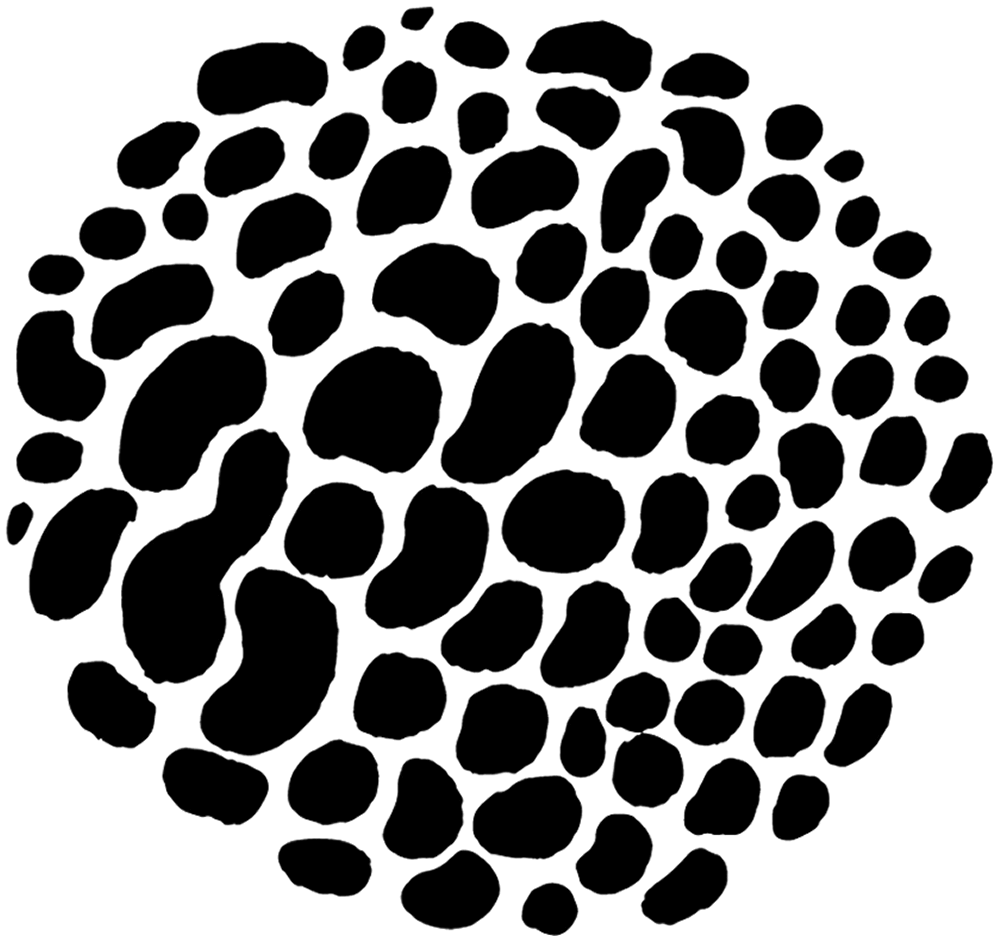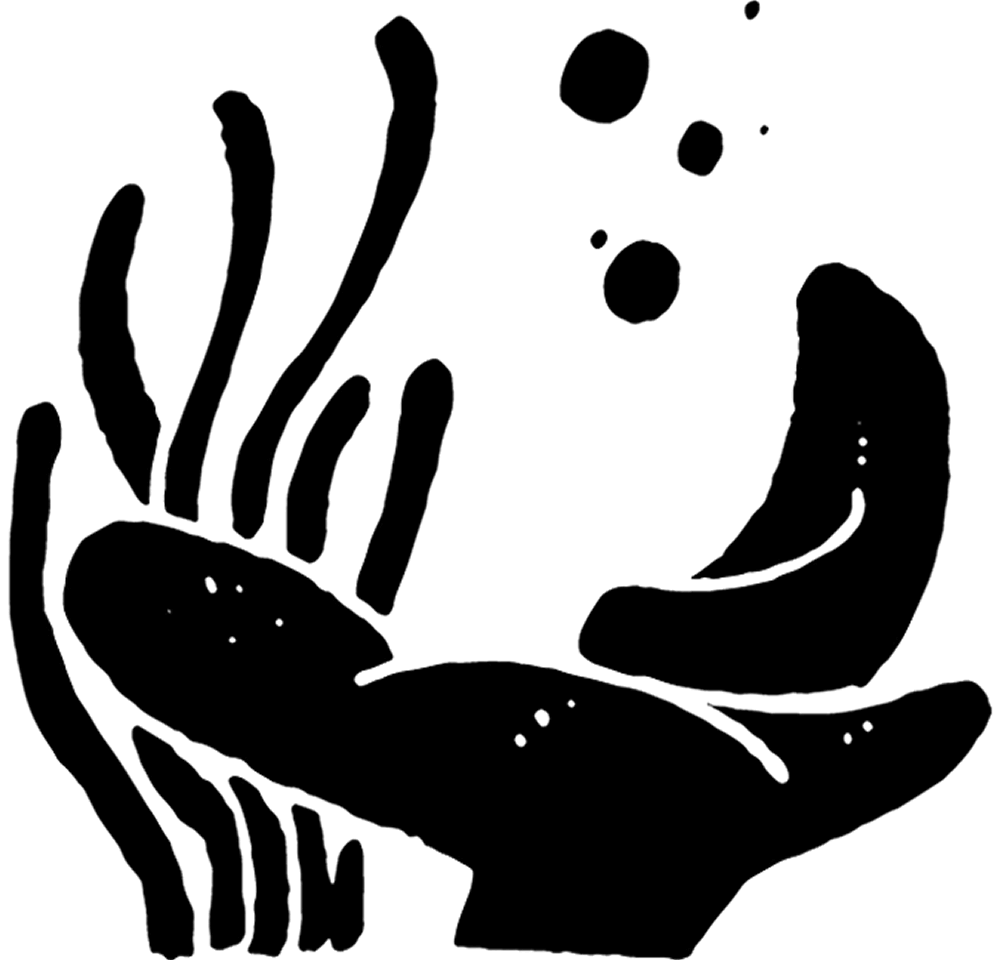多くの人々はリスク許容度を、考え方や選択、教育、自信、あるいは環境によって生まれるものだと考えています。しかし、もしそれがもっと深いところに根差しているとしたらどうでしょうか? もし私たちの中には、生まれつき他の人よりもリスクを取るように「配線」されている人たちがいるとしたら?
科学的には、リスク回避には遺伝的な要素があるという考え方がますます支持されています。双子を対象とした研究やゲノム全体にわたる解析によれば、ドーパミンやセロトニンの調節に関わる遺伝子が、私たちが報酬や危険をどのように認識するかに影響を及ぼすことが示唆されています。リスクを取る行動は、単なる学習の産物ではなく、遺伝的にも受け継がれています。
最も良く研究されてきた変異の1つが、ドーパミン4受容体遺伝子(DRD4)内に存在する48塩基対のリピート配列です。なかでも「7リピート(7R)」型は、新奇性追求傾向や衝動性、さらには金融・社会面でのリスクテイクの高さと関連しています。興味深いことに、このアレルの世界分布は極端に偏っており、アメリカ大陸では染色体のおよそ48%に見られる一方、東アジア(日本を含む)ではわずか約2%にとどまります。
なぜ、こんな差が? 進化生物学の研究によれば、7R アレルの出現頻度は人類の移動距離に呼応しており、アフリカを離れて最も遠くまで旅した集団ほど 7R の保有率が高いことが示されています。中立的な遺伝的浮動を考慮に入れても、この傾向は変わりません。言い換えれば、この遺伝子そのものが「歴史上、最も遠くへ動いた人々」とともにヒッチハイクしてきたのかもしれないのです。
重要なのは、7Rが単なる集団遺伝学上の例外的な変異では終わらない点です。会社を立ち上げる人々のあいだで、7Rは不釣り合いなほど高い頻度で見つかります。Nicolaouらによる大規模な双子研究では、7R保有者は自営業の経験を持つ割合がほぼ2倍に達することが示されています。さらに2021年の国際比較データセットでは、各国の7R出現率がアーリーステージの起業率の変動の約20%を説明していることが報告されています。
アメリカ合衆国は、より良い生活を求めてすべてを投げ打ち、より良い生活に賭けた人々が築いた国です。その決断は決して些細なものではありません。移民という行為自体が、家族や言語、文化、そして安全を捨てて未知の世界へ踏み出すという、極端なリスクテイクの形態です。代々にわたり、アメリカはリスクを取ることを厭わない人々が集まる場所となってきました。そこに何世紀にもわたるフロンティア開拓精神や起業家神話、そして個人主義文化が加わり、生物学的にも文化的にもリスク許容度が高い国になったのです。
さらにこの論理を一歩進めると、アメリカという国全体よりも西海岸のほうがリスク許容度が高いと考えるのは自然です。東海岸に到着した多くの人々が、そこからさらに西へ移動し続けました。カリフォルニアは一攫千金を夢見る開拓者たちや夢想家、そして現在ではスタートアップの起業家たちを引き寄せる磁石のような存在となりました。シリコンバレーの文化は偶然の産物ではありません。それは何世紀にもわたるリスクテイカーの移動が連綿と続いてきた結果なのです。
ここで日本と比較してみましょう。日本はその歴史の大半、特に江戸時代(1603年~1868年)において、外界に対してほぼ閉鎖的でした。移民はほとんどなく、徳川幕府は厳格な身分制度を強制し、社会的流動性を抑制し、混乱よりも調和と安定を重視していました。250年以上にわたって、日本はリスクテイカーを排除してきたのです。文化的にも、そしてもしかすると遺伝的なレベルでも、それは大きな影響を残したと言えるでしょう。念のために言えば、江戸時代は日本にも平和と繁栄をもたらし、GDPでも表れる経済成長と安定が見られました。これは称賛に値します。当時、世界各地が戦争に巻き込まれていたなかで、日本は人口約3000万人の国を大きな戦禍なく維持できたのです。
とはいえ、日本が自らを鎖国状態に置いた結果、技術革新は停滞しました。自国がどれほど後れを取っていたかに気づいたとき、初めて日本は再びリスクを取り、活力を取り戻す方向へと突き動かされたのです。
ここで、「でも日本は過去に大きなリスクを取ってきたではないか? 第二次世界大戦はどうなのか? 1980年代のバブル経済はどうなのか?」と反論する人もいるかもしれません。
もっともな疑問です。1930年代から40年代にかけての日本の軍国主義的な拡張は、確かにリスクの高いものでした。ただし、それは広く文化的にリスクを受け入れていたというよりも、上からの権威的な意思決定によって動かされていたのです。それは起業家的なリスクではなく、国家主義的かつ戦略的なものでした。一般市民にはほとんど意思決定の余地はなく、異を唱えることは非常に危険でした。一方で、1980年代の経済ブームは、戦後の数十年にわたる成長によって築かれた自信を反映したものでしたが、そこでのリスクテイクは主に企業や金融セクターに集中しており、草の根レベルのイノベーションではありませんでした。みんなが同じように行動していると、それが実際にはどれほどリスキーであっても、あるいは過剰なリスクによって状況がむしろ悪化していても、リスクが小さく感じられることがあります。バブルが崩壊した後、その反動として「混乱を避けようとする国民的な本能」がさらに強化されたのです。
現在に至るまで、日本の移民受け入れ数は他の多くの先進国に比べてはるかに低いままです。そして、日本は均質的で内向きな社会というイメージが依然として根強い。しかし、ここで興味深いのは、その現実が今まさに変わりつつあるという点です。
日本に在留する外国人の数は2024年に377万人という過去最高を記録し、10年前の約210万人から大幅に増加しました。これは非常に大きな伸びであり、推計によれば、外国生まれの人口比率は現在の約3%から2070年までに10%を超える可能性もあると言われています。そしてこれは全体像の一部にすぎません。日本の国勢調査では、民族や人種は調査対象ではなく国籍のみが記録されます。つまり、一度帰化して日本国籍を取得すると、その人は日本人として数えられるのです。したがって、実際には日本の多様性は表面上の統計よりも高いということになります。帰化した在日コリアンや中国系、東南アジア系の人々はもはや外国人としてはカウントされませんから、日本の真の多様性は表面的には見えにくいのです。最大のリスクテイカーとも言われるソフトバンクの孫正義氏は在日韓国人出身の日本人です。
もし米国が遺伝的にリスク志向だとするなら、制度面でもその特性を伸ばす「肥沃な土壌」が整っています。実際、新規ビジネスの約31%は移民によって立ち上げられ、アメリカのユニコーン企業の過半数には少なくとも1人の移民創業者がいます。日本に押し寄せる移民の波は、リスク許容というDNAを少しずつ列島に染み込ませるかもしれません。移民が増え続ければ、その小さなしずくが数十年をかけて目に見える変化を生む可能性があります。
ここから興味深い可能性が浮かび上がります。移民の増加が日本全体のリスクへの姿勢を徐々に変化させることはあり得るのでしょうか? それによって、より活気に満ちた社会や起業家精神の高まり、不確実性を避けるのではなく受け入れる文化が育まれることにつながるのでしょうか?
その可能性は十分に考えられます。もし移民がリスク許容度の高い人々の自己選抜によって成り立っており、その特性が部分的にでも遺伝するのであれば、アメリカでそうなったように、日本の「国民的DNA」も徐々に変化していくかもしれません。一朝一夕に実現することではありませんし、文化的な慣性は根強いですが、日本はもはや多くの人が考えるほど閉鎖的な国ではなくなりつつあります。
もちろん、活気の向上は同時に不安定さをもたらす可能性もあります。日本の社会的結束や低い犯罪率は、その均質性と集団志向の文化によるところが大きいのです。江戸時代は、そのことを証明しているとも言えるでしょう。今後の課題は、イノベーションと調和、変革と秩序をどのように両立させるかという点にあるでしょう。
しかし、忘れてはならないのは、移民は単なる経済的な手段ではないということです。それは心理的な影響力を持つ可能性もあります。そして長い時間をかけて、日本がリスクや機会、そして未来そのものを捉える方法を変えていくかもしれません。
日本は少子高齢化や労働力不足という問題に直面していますが、新たな「DNA」の流入によって、今後数十年の間に劇的な変化がもたらされる可能性があるのではないでしょうか。
Founding Partner & CEO @ Coral Capital